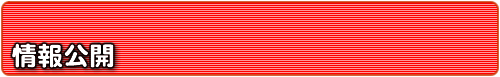
業務及び財務等に関する資料の公開
3,431名(令和4年4月1日現在)
| 支 部 (18) | 成田第1支部 | |
| 成田第2支部 | ||
| 成田第3支部 | ||
| 成田第4支部 | ||
| 富里支部 | ||
| 八街支部 | ||
| 佐倉支部 | ||
| 志津支部 | ||
| 臼井支部 | ||
| 四街道支部 | ||
| 酒々井支部 | ||
| 印西支部 | ||
| 栄支部 | ||
| 印旛支部 | ||
| 本埜支部 | ||
| 白井支部 | ||
| 大栄支部 | ||
| 下総支部 | ||
| 委員会 (5) | 組織委員会 | |
| 厚生事業委員会 | ||
| 指導委員会 | ||
| 財政委員会 | ||
| 広報委員会 | ||
| 部 会 (3) | 女性部 | |
| 青年部 | ||
| 農業部 | ||
職員7名(パート含む)(令和4年5月1日現在)
|
正会員
|
年額
|
15,000円
|
(入会金3,000円) |
|
準会員
|
年額
|
7,500円
|
|
第 1 章 総 則
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (名 称) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 1 条
|
この法人は、一般社団法人成田青色申告会(以下「本会」という。)と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (事務所) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 2 条
|
本会は、主たる事務所を千葉県成田市に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第 2 章 目的及び事業
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(目 的)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
第 3 条
|
本会は、健全な納税者団体として、誠実な記帳の普及に努め、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑の執行に寄与し、併せて事業経営と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (事 業) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 4 条
|
本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
第 3 章 会 員
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (法人の構成員) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 5 条
|
本会の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (会員の資格の取得) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 6 条
|
本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により、任意に入会することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (経費の負担) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 7 条
|
会員は、社員総会(以下「総会」という。)の決議を経て別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。 2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。 |
||||||||||||||||||||||||||
| (退会) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 8 条
|
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (除名) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 9 条
|
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。 |
||||||||||||||||||||||||||
| (会員資格の喪失) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 10 条
|
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
第 4 章 総 会
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (構成) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 11 条
|
総会はすべての正会員をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (権限) | |||||||||||||||||||||||||||
第 12 条 |
総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)理事及び監事の報酬等の額 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算表)の承認 (5)定款の変更 (6)解散及び残余財産の処分 (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
||||||||||||||||||||||||||
| (開催) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 13 条
|
本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
前項の定時総会をもって法人法上の社員総会とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (招集) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 14 条
|
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求する事ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
総会を招集するには、会長は総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (議長) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 15 条
|
総会の議長は出席理事の中から会長が指名する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (議決権) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 16 条
|
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (決議) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 17 条
|
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他、法令で定められた事項 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (総会における書面決議) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 18 条
|
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって決議することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
前項の場合における前条の規程の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (議事録) | |||||||||||||||||||||||||||
第 19 条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
議長及び議長が指名する総会に出席した理事2名 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第 5 章 役員
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (役員の配置) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 20 条
|
本会に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上30名以内 (2) 監事 1名以上3名以内 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
理事のうち1名を会長、6名以内を副会長とし、必要と認める場合は専務理事を1名置くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (役員の選任) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 21 条
|
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (理事の職務及び権限) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 22 条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
会長、副会長及び専務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (監事の職務及び権限) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 23 条
|
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (役員の任期) | |||||||||||||||||||||||||||
第 24 条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は、辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事の権利義務を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (役員の解任) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 25 条
|
理事及び監事は、総会の決議によって解任する事ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (報酬等) | |||||||||||||||||||||||||||
|
第 26 条
|
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には、総会において別に定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (顧問及び相談役) | |||||||||||||||||||||||||||
第 27 条 |
本会に、顧問及び相談役(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。 |
||||||||||||||||||||||||||
2 |
名誉役員は理事会の決議により会長がこれを委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
名誉役員は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
名誉役員の報酬は、無償とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
名誉役員について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第 6 章 理事会
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(構成)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
第 28 条
|
本会に理事会を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 名誉役員は、会長の求めに応じ理事会に出席し意見を述べることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(権限)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
第 29 条
|
理事会は次の職務を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
(招集)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 30 条 | 理事会は会長が招集する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(決議)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 31 条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||
(議事録)
|
|||||||||||||||||||||||||||
第 32 条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 議事録には、理事会に出席した会長及び監事がこれに署名する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第 7 章 委員会、支部及び部会
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(委員会)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
第 33 条
|
本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、理事会の推薦により、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 委員会の名称、構成、権限及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(支部)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 34 条 | 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 支部長は、支部の推薦を参考に、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代表者又はその役員)のうちから理事会が選任する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 支部の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(部会)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 35 条 | 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、部会を設置することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 部会の部会長は、部会の推薦を参考に、会員(会員が法人その他の団体である場合にはその代表者又はその役員)のうちから理事会が選任する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 部会の名称、構成、任務及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第 8 章 事務局
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(事務局)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 36 条 | 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な数の職員を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 事務局には、事務局長を置き、理事会の決議により会長が任免する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 職員は会長が任免する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
第 9 章 資産及び会計 |
|||||||||||||||||||||||||||
(事業年度) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 37 条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(事業計画及び収支予算)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 38 条 | 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度の終了までの間、備え置くものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(事業報告及び決算)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 39 条 | 本会の、事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(剰余分の分配制限)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 40 条 | 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第 10 章 定款の変更及び解散
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(定款の変更)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 41 条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(解 散)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 42 条 | 本会は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(残余財産の処分)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 43 条 | 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第 11 章 情報公開及び個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||
(情報公開) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 44 条 | 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
(個人情報の保護) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 45 条 | 本会は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第 12 章 公告
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(公告の方法)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第 46 条 | 本会の公告は、電子公告により行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
附 則
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本会の最初の代表理事は、山田謙四郎とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
令和4年 度
|
理 事
|
(会 長)
|
片 岡 英 雄 |
|
同
|
( 副会長 )
|
寺 嶋 道 幸 |
|
同
|
( 同 )
|
石 原 昭 次 |
|
同
|
( 同 )
|
小 関 智 之 |
|
同
|
( 同 )
|
根 本 久仁男 |
|
同
|
( 同 )
|
粟飯原 正 直 |
同 |
( 同 ) |
程 田 正 己 |
|
同
|
香 取 正 勝 | |
|
同
|
川 野 晴 司 | |
|
同
|
長谷川 攝 子 |
|
|
同
|
今 井 牧 子 | |
同 |
秋 山 秀 恒 | |
同 |
石 井 功 次 | |
同 |
小 貫 重 政 | |
同 |
浅 野 勝 男 | |
| 同 | 大 門 範 行 | |
| 同 | 飯 塚 好 二 | |
|
顧 問
|
増 田 實 | |
顧 問 |
山 田 謙四郎 | |
|
監 事
|
堀 越 健 一 |
令和3年度 |
(単位 万円) |
| 収入の部 | ||
| 会費等収入 | 5,456 |
|
| 事業収入 | 760 |
|
| その他収入 | 2 |
|
| 当期収入合計(A) | 6,218 |
|
| 前期繰越収支差額 | 1,082 |
|
| 収入合計(B) | 7,300 |
|
| 支出の部 | ||
| 事業費 | 4,167 |
|
| 管理費 | 1,106 |
|
| その他支出 | 732 |
|
| 当期支出合計(C) | 6,005 |
|
| 当期収支差額(A)-(C) | 213 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,295 |
|
令和2年度 |
(単位 万円) |
| 収入の部 | ||
| 会費等収入 | 5,605 |
|
| 事業収入 | 798 |
|
| その他収入 | 0 |
|
| 当期収入合計(A) | 6,403
|
|
| 前期繰越収支差額 | 192 |
|
| 収入合計(B) | 6,595 |
|
| 支出の部 | ||
| 事業費 | 4,078 |
|
| 管理費 | 1,178 |
|
| その他支出 | 213 |
|
| 当期支出合計(C) | 5,469 |
|
| 当期収支差額(A)-(C) | 934 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,126 |
|
令和元年度 |
(単位 万円) |
| 収入の部 | ||
| 会費等収入 | 4,922 |
|
| 事業収入 | 1,012 |
|
| その他収入 | 24 |
|
| 当期収入合計(A) | 5,958 |
|
| 前期繰越収支差額 | 274 |
|
| 収入合計(B) | 6,232 |
|
| 支出の部 | ||
| 事業費 | 4,213 |
|
| 管理費 | 1,754 |
|
| その他支出 | 73 |
|
| 当期支出合計(C) | 6,040 |
|
| 当期収支差額(A)-(C) | -82 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 192 |
|
平成30年度 |
(単位 万円) |
| 収入の部 | ||
| 会費等収入 | 5,026 |
|
| 事業収入 | 889 |
|
| その他収入 | 24 |
|
| 当期収入合計(A) | 5,939 |
|
| 前期繰越収支差額 | 365 |
|
| 収入合計(B) | 6,304 |
|
| 支出の部 | ||
| 事業費 | 4,263 |
|
| 管理費 | 1,695 |
|
| その他支出 | 72 |
|
| 当期支出合計(C) | 6,030 |
|
| 当期収支差額(A)-(C) | -91 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 274 |
|
平成29年度 |
(単位 万円) |
| 収入の部 | ||
| 会費等収入 | 5,098 |
|
| 事業収入 | 925 |
|
| その他収入 | 24 |
|
| 当期収入合計(A) | 6,047 |
|
| 前期繰越収支差額 | 221 |
|
| 収入合計(B) | 6,268 |
|
| 支出の部 | ||
| 事業費 | 4,138 |
|
| 管理費 | 1,692 |
|
| その他支出 | 72 |
|
| 当期支出合計(C) | 5,902 |
|
| 当期収支差額(A)-(C) | 145 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 365 |
|
[注] 金額は万円未満を四捨五入しました。
令和3年度 |
(単位 万円) |
| 増加の部 | ||
| 経常収益 | 6,216
|
|
| 経常外収益 | 0 |
|
| 経常収益計 | 6,216 |
|
| 減少の部 | ||
| 経常費用 | 5,422 |
|
| 経常外費用 | 150 |
|
| 減少額合計 | 5,572 |
|
| 当期正味財産増加額 | 644 |
|
| 前期繰越正味財産額 | 6,384 |
|
| 期末正味財産合計額 | 7,028 |
|
令和2年度 |
(単位 万円) |
| 増加の部 | ||
| 経常収益 | 6,403
|
|
| 経常外収益 | 0 |
|
| 経常収益計 | 6,403 |
|
| 減少の部 | ||
| 経常費用 | 5,344 |
|
| 経常外費用 | 150 |
|
| 減少額合計 | 5,494 |
|
| 当期正味財産増加額 | 908 |
|
| 前期繰越正味財産額 | 5,475 |
|
| 期末正味財産合計額 | 6,384 |
|
令和元年度 |
(単位 万円) |
| 増加の部 | ||
| 経常収益 | 5,958 |
|
| 経常外収益 | 0 |
|
| 経常収益計 | 5,958 |
|
| 減少の部 | ||
| 経常費用 | 6,156 |
|
| 経常外費用 | 45 |
|
| 減少額合計 | 6,201 |
|
| 当期正味財産増加額 | -243 |
|
| 前期繰越正味財産額 | 5,718 |
|
| 期末正味財産合計額 | 5,475 |
|
平成30年度 |
(単位 万円) |
| 増加の部 | ||
| 経常収益 | 5,940 |
|
| 経常外収益 | 0 |
|
| 経常収益計 | 5,940 |
|
| 減少の部 | ||
| 経常費用 | 6,147 |
|
| 経常外費用 | 45 |
|
| 減少額合計 | 6,192 |
|
| 当期正味財産増加額 | -252 |
|
| 前期繰越正味財産額 | 5,970 |
|
| 期末正味財産合計額 | 5,718 |
|
平成29年度 |
(単位 万円) |
| 増加の部 | ||
| 経常収益 | 6,046 |
|
| 経常外収益 | 0 |
|
| 経常収益計 | 6,046 |
|
| 減少の部 | ||
| 経常費用 | 6,018 |
|
| 経常外費用 | 45 |
|
| 減少額合計 | 6,063 |
|
| 当期正味財産増加額 | -17 |
|
| 前期繰越正味財産額 | 5,987 |
|
| 期末正味財産合計額 | 5,970 |
|
[注] 金額は万円未満を四捨五入しました。
令和4年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 2,623
|
|
| 固定資産 | 7,297 |
|
| 資産合計 | 9,920 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 828 |
|
| 固定負債 | 2,065 |
|
| 負債合計 | 2,893 |
|
| 正味財産の部 | ||
| 正味財産 | 7,028 |
|
| 負債及び正味財産合計 | 9,920 |
|
令和3年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 1,971
|
|
| 固定資産 | 6,666 |
|
| 資産合計 | 8,636 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 388 |
|
| 固定負債 | 1,865 |
|
| 負債合計 | 2,253 |
|
| 正味財産の部 | ||
| 正味財産 | 6,383 |
|
| 負債及び正味財産合計 | 8,636 |
|
令和2年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 994
|
|
| 固定資産 | 6,492 |
|
| 資産合計 | 7,486 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 346 |
|
| 固定負債 | 1,665 |
|
| 負債合計 | 2,011 |
|
| 正味財産の部 | ||
| 正味財産 | 5,475 |
|
| 負債及び正味財産合計 | 7,486 |
|
平成31年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 1,165
|
|
| 固定資産 | 6,549 |
|
| 資産合計 | 7,714 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 391 |
|
| 固定負債 | 1,605 |
|
| 負債合計 | 1,996 |
|
| 正味財産の部 | ||
| 正味財産 | 5,718 |
|
| 負債及び正味財産合計 | 7,714 |
|
平成30年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 1,206
|
|
| 固定資産 | 6,650 |
|
| 資産合計 | 7,856 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 341 |
|
| 固定負債 | 1,545 |
|
| 負債合計 | 1,886 |
|
| 正味財産の部 | ||
| 正味財産 | 5,970 |
|
| 負債及び正味財産合計 | 7,857 |
|
[注] 金額は万円未満を四捨五入しました。
令和4年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 2,623
|
|
| 固定資産 | 11,669 |
|
| 資産合計 | 14,292 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 828 |
|
| 固定負債 | 6,436 |
|
| 負債合計 | 7,264 |
|
| 正味財産 | 7,028 |
|
令和3年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 1,971
|
|
| 固定資産 | 11,247 |
|
| 資産合計 | 13,218 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 388 |
|
| 固定負債 | 6,446 |
|
| 負債合計 | 6,834 |
|
| 正味財産 | 6,384 |
|
令和2年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 994
|
|
| 固定資産 | 11,034 |
|
| 資産合計 | 12,028 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 346 |
|
| 固定負債 | 6,207 |
|
| 負債合計 | 6,553 |
|
| 正味財産 | 5,475 |
|
平成31年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 1,165
|
|
| 固定資産 | 10,917 |
|
| 資産合計 | 12,082 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 391 |
|
| 固定負債 | 5,973 |
|
| 負債合計 | 6,364 |
|
| 正味財産 | 5,718 |
|
平成30年3月31日現在 |
(単位 万円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 1,207
|
|
| 固定資産 | 10,844 |
|
| 資産合計 | 12,051 |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 342 |
|
| 固定負債 | 5,739 |
|
| 負債合計 | 6,081 |
|
| 正味財産 | 5,970 |
|
[注] 金額は万円未満を四捨五入しました。
事業活動基本方針
1
新規会員増強運動を強力に展開すると共に、引続き新型コロナウイルスによる感染防止に努め会員の安全を第一に事業を展開する。
2
3
4
税務当局との信頼を基調に電子申告(e-Tax)の普及に努め、税務行政の円滑な運営に協力する。
5
6
社会保障・マイナンバー制度の定着に向け周知を図る。
7
女性部、青年部の充実強化を図り、後継者の指導育成に努める。
8
9
働き方の多様化やコロナ禍の厳しい環境にあって、個人事業主が事業を継続・発展していくためには、税制・社会保障制度の整備が急がれる。全青色の指導方針に則り、個人事業主のための税制改正運動を推進する。
10
会員親睦行事等を通じて相互の連携意識を高め、融和協調を図る。
11
12
13
|
令和4年度 |
|
(単位 万円) |
| 収入の部 | ||
| 会費等収入 |
5,437 |
|
| 事業収入 |
664
|
|
| その他収入 |
210
|
|
| 当期収入合計(A) | 6,311 |
|
| 前期繰越収支差額 |
1,295
|
|
| 収入合計(B) |
7,606
|
|
| 支出の部 | ||
| 事業費 | 4,521 | |
| 管理費 |
1,594
|
|
| その他支出 |
313 |
|
| 当期支出合計(C) |
6,428 |
|
| 当期収支差額(A)-(C) |
-117
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
1,178
|
|
[注] 金額は万円未満を四捨五入しました。